2025年放送のTBS日曜劇場『御上先生』は、エリート官僚教師・御上孝(松坂桃李)が教育現場の腐敗と対峙する姿を描く話題作。
第5話では、高校生ビジネスプロジェクトコンクールを巡って、生徒たちが忖度を超えたプレゼンを披露し、御上と共に“社会の壁”に挑みます。
さらに、事件を起こした真山弓弦(堀田真由)の過去も描かれ、彼女と向き合う神崎の姿が印象的な回となりました。本記事では第5話のネタバレあらすじ、視聴者の感想、見どころ、キャストの演技などを詳しく解説します。
- 高校生たちの本気プレゼンと“社会への挑戦”
- 真山弓弦の過去と神崎の心の変化
- 教育と社会が交錯する“言葉の力”の意味
御上先生第5話ネタバレ|“金融ドラマ”への痛烈プレゼンと弓弦の過去が交差する
第5話では、ビジネスコンテストを舞台に、生徒たちのプレゼンが社会への“宣戦布告”のような熱を帯びて展開されます。
その一方で、真山弓弦の過去を掘り下げる面会シーンが挿入され、物語は教育と社会、そして個人の選択という三層構造に踏み込んでいきます。
“忖度ナシ”の発言が飛び出すプレゼンと、弓弦の罪に向き合おうとする若者たちの姿が交差し、本作の核心に迫る回となりました。
高校生が挑む“忖度ナシ”のビジネスコンテスト
第5話の主軸は、高校生によるビジネスプロジェクトコンテスト。
生徒たちは隣徳学院を代表して発表するという立場にありながらも、一切の忖度を排除した“本気の提案”に挑みます。
冬木・宮澤・徳守らが率いるチームは、社会問題をテーマにした提案を通じて、会場に鋭いメッセージを突き付けました。
単なる優勝を狙う発表ではなく、「社会に何を伝えたいか」が明確に伝わる姿勢に、多くの視聴者が感銘を受けたはずです。
「倍返ししてる場合じゃない」金融批判が炸裂
プレゼンの中で、ある生徒が語った「倍返ししてる場合じゃない」というセリフがSNSで大きな話題を呼びました。
これは明らかに、TBSの名作『半沢直樹』へのオマージュでありながら、金融機関による過剰な報復構造や権威主義への批判でもありました。
観客も息をのむようなこの瞬間は、教育の現場から社会に“ノー”を突きつける強烈なインパクトを残しました。
視聴者からは「TBS、内部で喧嘩売ってて笑った」「攻めすぎてて逆に清々しい」といった声も多く見られました。
真山弓弦の過去に迫る面会シーンの緊迫感
コンテストの華やかな空気とは対照的に、神崎は真山弓弦との面会を重ね、彼女の過去に迫っていきます。
「なぜ事件を起こしたのか」「母親に対してどうしても許せなかったものは何か」——弓弦の核心にある孤独と絶望が、淡々とした口調の裏に滲んでいました。
神崎がただの報道志望の学生から、誰かの痛みに耳を傾ける“人”へと成長していく様子も印象的です。
視聴者にとっても、「罪と向き合うことの意味」を深く考えさせられる重厚なパートとなっていました。
第5話の見どころと視聴者の感想まとめ
第5話では、生徒たちのプレゼンと、弓弦との対話という“動”と“静”の二つのドラマが交錯し、作品としての奥行きがさらに広がりました。
これまで積み重ねてきたキャラクターの成長が一気に花開くような演出も多く、視聴者の心に強く残るエピソードとなっています。
SNSやレビューサイトにはさまざまな感想が寄せられ、TBSらしい挑戦的な演出への評価も高まっています。
「半沢直樹ディス」にネット騒然!TBS内での挑戦
前項でも触れたように、「倍返ししてる場合じゃない」というセリフが話題の中心に。
この台詞は、“スカッと感”だけを求めるドラマへのアンチテーゼとも受け取れるものでした。
実際にX(旧Twitter)では、「TBSの自虐?」「よくこの脚本通したな…!」と局内からの自己批判的な試みに驚く声が押し寄せた。
それだけでなく、「こっちの方がリアルで刺さる」「高校生の口から言わせたのがすごい」など、演出への賞賛も相次ぎました。
神崎の成長とプレゼンで見せた熱意に称賛の声
神崎(奥平大兼)の存在感がますます増しているのも、第5話の見どころのひとつです。
プレゼンでは、彼自身が「社会を批判することの意味」「責任ある発言とは何か」を真剣に考え抜いた上で登壇。
熱意が伝わる目線や、言葉を選びながら語る姿に、視聴者の多くが心を動かされました。
「最初の頃の神崎からは想像できない成長ぶり」「涙出た」「リアル高校生の代表みたい」といった声も多く、彼の変化は多くの人の記憶に残ったようです。
注目キャストの演技と名シーン
第5話はテーマ性の強さだけでなく、キャスト陣の熱演によって、物語にリアリティと深みが加わった回でもありました。
特に、堀田真由・奥平大兼をはじめとする若手キャストの存在感が際立ち、視聴者からも演技に対する称賛の声が多く上がっています。
また、プレゼンシーンでの複数キャラの同時躍動も印象的で、群像劇としての完成度を高める要素となっていました。
堀田真由が演じる弓弦の哀しみと静かな怒り
第5話では、真山弓弦(堀田真由)の内面に一歩踏み込む描写が加わり、“犯人”というレッテルの裏にある孤独が浮き彫りになります。
堀田の演技は、感情をあからさまに見せることなく、目線や沈黙の使い方で哀しみや怒りを表現しており、多くの視聴者が引き込まれました。
「あの無言の瞬間にすべて詰まってた」「台詞よりも強い演技」とSNSでも絶賛され、女優としての実力が再評価されるきっかけとなっています。
奥平大兼が演じる神崎の変化と挑戦
神崎の演技は回を追うごとに深化しており、第5話では特に「プレゼン」と「面会」の対比によって彼の成長が強調されていました。
強く語る一方で、人の痛みに耳を傾ける優しさを併せ持つ姿に、感情移入した視聴者も多かったことでしょう。
視聴者からは「こんなに演技で泣かされたの久々」「神崎に未来を託したくなる」といったコメントも多く、奥平の演技に対する信頼が着実に育っています。
プレゼンシーンで輝いた冬木・宮澤・徳守役の俳優たち
冬木・宮澤・徳守の3人が率いるプレゼンチームは、第5話のドラマ性とエンタメ性を象徴する存在でした。
それぞれのキャラクターが持ち味を発揮しつつ、一つのチームとして説得力あるメッセージを打ち出した瞬間は、本作屈指の名シーンに。
若手俳優たちの勢いとリアリティが見事に融合し、画面越しでもプレゼンの熱が伝わってきました。
「演技なのに本当の高校生みたい」「このまま起業してもいいくらいの迫力」と、彼らの熱演に対する評価も非常に高いです。
御上先生第5話が伝える教育と社会の“ねじれ”
第5話は、ビジネスコンテストという現代的な題材を通じて、教育の理想と社会の現実の“ねじれ”に深く切り込みました。
生徒たちは「正解」を求める授業ではなく、自分たちで問いを立て、答えを創り出すプロセスに向き合うことで、大きな成長を遂げていきます。
一方で、学校や大人たちがどこまでそれを支えられているかという構造的な課題も浮き彫りになりました。
ビジネス教育を通じて問いかける「本当の社会性」
コンテストのプレゼンでは、マーケティング理論やプレゼン技術だけでなく、社会的課題をどう伝えるかという視点が重視されていました。
これはまさに、“生きた教育”としての社会性を育む実践の場です。
御上が語った「言葉を磨くとは、他人の立場になって考えることだ」という言葉も、プレゼンの根底に流れるテーマを象徴しています。
視聴者からも「学校でこんな教育あったらいいのに」「子どもに見せたいドラマ」といった声が続々と寄せられています。
教育現場に潜む“忖度”と御上の問いかけ
御上は、生徒たちに「社会を忖度するな」と言う一方で、大人たちが“現実”という名の忖度を教育現場に持ち込んでいることにも強く疑問を投げかけています。
これは教育の名のもとに“大人の都合”を押しつけているという、痛烈な自己批判でもあります。
御上自身もまた、その構造に加担していた一人として葛藤を抱えていることが示唆されており、本作の深さが垣間見えました。
「教師も生徒も、“答えを持たないまま”問い続けることが大事」——このメッセージは、教育に携わるすべての人に届く言葉ではないでしょうか。
御上先生第5話の内容と感想・弓弦と生徒たちの行方まとめ
第5話は、ビジネスコンテストという“建前のない舞台”を通して、生徒たちの可能性と葛藤を鮮明に描いた回でした。
その一方で、真山弓弦という存在の痛みと向き合おうとする神崎の姿は、教育が人の心にどう寄り添えるのかを問いかけています。
本作の本質である「教育と社会の交差点」が、より明確になった印象的な回となりました。
プレゼンという表現の場に立った生徒たちは、それぞれの想いや視点を“言葉の力”で伝えきりました。
その内容が賞を取ったかどうか以上に、「社会に何を届けたいか」を真剣に考えた過程が、視聴者の心を動かしたのです。
「感動で泣いた」「教育ドラマでここまで熱くなれるとは思わなかった」という声も多く、今後の展開への期待感を高める内容でした。
また、弓弦との面会シーンでは、事件の核心にはまだ触れていないものの、彼女の抱えていた“沈黙の理由”が少しずつ言葉になり始めています。
神崎や御上との対話が、彼女の内面を溶かしていく過程は、今後の物語の鍵になることでしょう。
「誰もが正義を持っている。でもその正義は、時に誰かを追い詰める」――そんな複雑な社会の中で、教育の意味を問い直すこの作品の挑戦は、まだまだ続きます。
- 高校生たちが本気のプレゼンで社会に挑む
- 「倍返ししてる場合じゃない」が話題に
- 弓弦の過去に迫る面会シーンが心を打つ
- 神崎の成長が視聴者に強い印象を残す
- 堀田真由の無言の演技に称賛の声
- 教育と社会の“ねじれ”に鋭く切り込む展開
- 御上の言葉が“言葉の力”の本質を示す
- 「答えより問い続ける姿勢」を教育の核心に

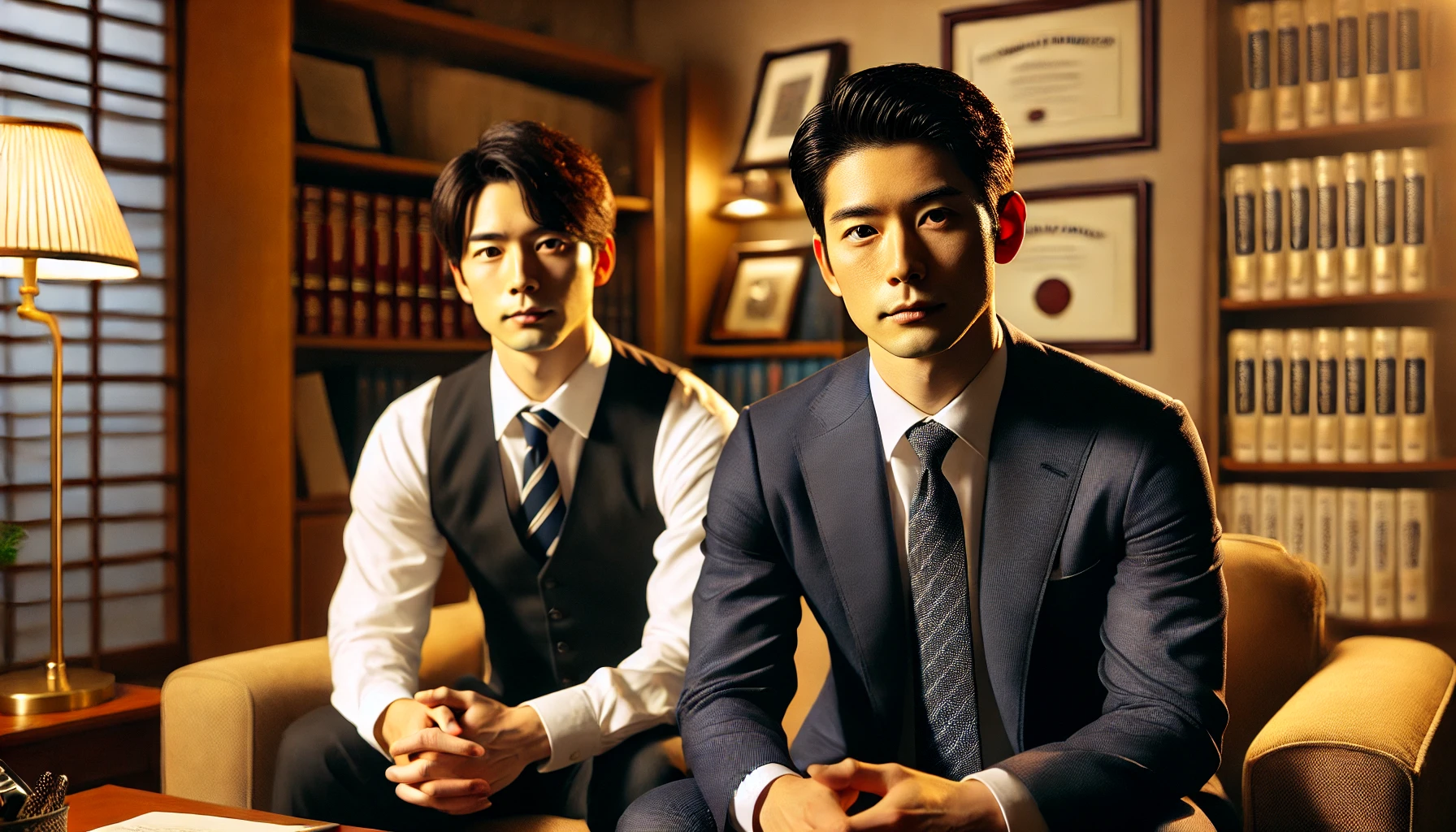


コメント